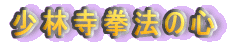
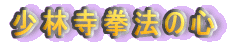
今も我々に語りかける開祖の言葉
![]()
この複雑で不安のつきまとう現代社会において、
今、開祖が生きていらっしゃったなら、何をおっしゃるだろうか。
開祖 宗道臣(そう どうしん)の言葉を紹介しながら、
人間のあるべき姿を考えたい。
![]()
「半(なか)ばは自己の幸せを 半ばは他人(ひと)の幸せを」 少林寺拳法をしている拳士なら誰もが知っている、開祖の代表的な言葉です。少林寺拳法は、1947年(昭和22年)、戦争を体験した開祖の志によって創られました。人づくりの道としての少林寺拳法を、思想の面からも広く知っていただきたいと思います。人間味あふれる開祖の言葉を、感じていただけたら幸いです。 合掌
「今、人間がいちばんしなければならないことは、殺し合いではない。世の中をよくするということは、やはり人間同士が英知を働かせてね、自分の幸せも考えるが、自分以外の他人の幸せも考えるような、そういう人間を増やす以外に方法がないということを私は見つけた。自分の体験からね。」(1966年の法話)
「拝むことや神仏の懲らしめを説くことが宗教ではないのです。ほんとうの宗教とは、自分をよりどころにして、いい人間をつくり、いい人間を増やす運動をすることだ。そして『人間の心の改造によって、この世に理想郷を作ろう』、他人の犠牲の上に自分だけが幸せになろうではなく、『半ばは自己の幸せを、半ばは他人の幸せを』というのが少林寺の考え方なのです。」(1969年 指導者講習会の法話)
「ささやかな自分の幸せや自分の利益以外は気にならない、そんな人ばかりだったら、世の中はけして良くならないし、前に進みません。また、考え方、生き方が違うなら抹殺してしまえ、邪魔な奴には何も発言させるな、では、世の中さらに悪くなるだけです。どっちつかずでもない、己のことと同時に他人のことも考えられる、日本だけではなくほかの国・民族のことも考えられる、そういう人間でありたい。また、そのために、一人ひとりの価値観を変えていこうじゃないか。」(1973年 大学支部合宿の法話)
「恥を失った人間はダメなのです。恥ずかしいということを意識できるような人間になる。そして、自分がそうであるように、他人にもそうなってもらうように影響を与える人生、これが尊敬される人生につながるのです。馬鹿にされず、胸をはっていられる生き方は、金や勲章ではないのです。」(1978年 武専卒業式の法話)
「しっかりせえよ。無気力な奴が増えとるから、日本はダメなのだ。わしみたいにな、死ぬまで負けたんではない、とことんやってみよう、という気が欠けとるな。世の中ってのは実はたいへんなとこなのだ。試合で勝ったって、そんなこと意味がない。」(1969年 本部武専の法話)
「弱いものいじめじゃなくて、強いものに噛みついても弱いものはかばってやれるようなすばらしいリーダーになりたいと、自分でそういうふうに思って努力すれば必ずなれる。他人のせいや、家柄や親のせいにするなよ。社会のせいでもない。自分の人生を自分で歩んでいるのだ。」(1979年の法話)
「君らを見ててつくづく思うんだが、豊かな中で育ったせいか、君たちはどこか投げやりだし、”まあまあ、どうでもいいや”式のがほんとうに多い。だから、姿や顔つきにしても表情がない。若いときは張りがあってあたりまえなのに、何か全体的に緩んだ印象を受ける。本気の喧嘩もできない、怒るべきときに怒れない、そんな不甲斐ないのは値打ちがないぞ、と厳しく言ったが、君らは人間なんだ。だったらもう少々でも人間らしくあってほしい。」(1973年 全国指導者講習会の法話)
― 以上『会報少林寺拳法』2002年8月1日発行 28頁〜33頁より抜粋
「原爆の時代、大量殺戮の時代にね、無手の格闘技に価値があるなんて思うのがおかしい。人を殺すなら、もっとよい方法がいっぱいある。人を生かし、人に生き甲斐や喜びを与え、自分もそれを享受できる道は、金剛禅運動においてしかないことは、みんなが知っていることである。金で得られないもの、勲章よりも尊いもの、誇りとか自信とか、最後の寄り所を自分に持てるような、人間をつくる道としての少林寺拳法なのです。」
(1975年8月 大学合宿 「あらはん」1983年10月号掲載)
「人間が行う最低のモラルの基準である。年寄りか子供を背負って、立っている人間の姿を向かい合わせ、ひとりでは生きていけない人間の形を示したのが行なのです。
行というものはね、最低限度人間として生きてゆくために必要なことである。それをやるには敵をやっつけたり、後輩をやっつける必要はない。後輩を育てる、先輩も立てる。そして自分の存在を認める。これが行なのである。これさえ行えないような学校なら、少林寺拳法部なんてのはいらないと思う。」
(1979年8月 夏季大学合宿 「あらはん」1984年10月号掲載)
「私が主張しておるように、武道とかスポーツというものには限界がある。それは、強くなるということには価値がある。記録を更新することには価値がある。
しかしね、かりに百メートルを何秒かで泳いだって、イルカにはかなわないんだよ。いいかね。船がひっくり返ったとき、荒海の中でみんなが助かるということには全然つながらない。わかるね。
何が目的で練習するのか。選手つくったって、バタフライをなんぼやったって、山登りをなんぼやったてだ、ウルトラBかCか知らんけどトンボ返りを何遍やってみたって、そんなことは日常生活や人民の幸せには全然つながらない。
だから、そういうものとは違うものを私たちはつくってきた。」
(1979年8月 夏季大学合宿 「あらはん」1984年11月号掲載)
「一人のいい息子が生まれたということによって、家庭がころっと変わります。一人のぐれた前科者が出ると、その家庭がみんな迷惑する。こういうことは諸君の周辺にごろごろしているでしょう。すぐれたもの一人がいかに重要かということである。
我々は、そのすぐれた人間にまず自らをおこうではないか、そして周辺にもいい影響を与えようではないか、こういう教えなのだ。」
(1966年8月 第一次指講 「あらはん」1982年11月号掲載)
「この世の中のこと、すべて人間が行い、人間が支配し、管理し、計画しておる。人間の質の問題ですよ、これはね。よくなるのもよくならんのも、要するに一人ひとり、そのポストに立っておる人の心の持ち方にある。こういうことで心の改造をやろうとしているのが宗教、特に金剛禅の大特徴である。」
(1966年8月 第一次指講 「あらはん」1982年11月号掲載)
「人間関係の中で一番大切なのはね、何かあったときにしてくれる、してもらえる、あるいはしてやりたい、こういうことじゃないか。俺がやられたら助けてくれ、お前がやられる時は知らん顔をしてるじゃ、友だち一人だってできゃせんぞ。なにかあったらかばってやる。それをできない人が多いから日本は駄目なのだ。私が行動せいというのは、そういうことを言いよるわけです。」
(1969年10月 第三次指講 「あらはん」1982年5月号掲載)
「それでね君たち、こういう精神生活に入ろうではないか。今日から。たとえば身体の切り傷、古傷はもう忘れてしもうとる。どうもないな。忘れてしまえ。肉体の傷と同じように、心の傷も今日から忘れようではないか。
いままでの生活の中で、挫折感に陥るようなことがある。ところがこれは、なんぼ考えたって昨日のことは取り返せるか。別れた彼女のこと、就職しそこねたことを悩んでみたって仕様がないじゃないか。昨日は昨日、今日は今日、明日は明日だ。これが精神生活を改造する根本になるんだよ。過去は一切、今日から忘れろ。
いいことは忘れんでいい。いやなことは忘れてしまえ。忘れようと努力しろ。とにかく気分転換することを勉強せい。」
(1969年8月 整法講習 「あらはん」1983年3月号掲載)
―以上『少林寺拳法副読本』172頁〜184頁より抜粋
![]()
 少林寺拳法とは 武道のあり方 武とは ほんとうの強さとは すべては人の質
少林寺拳法とは 武道のあり方 武とは ほんとうの強さとは すべては人の質